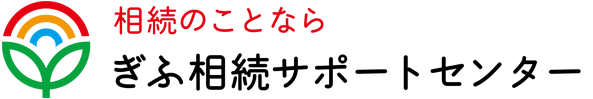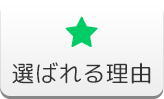税務署から相続税のお尋ねが来ない?相続税のお知らせが届く基準は?
目次 [非表示]
税務署から相続税のお尋ねが来ない?
ご家族が亡くなって数か月後に、税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届く場合があります。
この税務署からの文書は、いったいどのようなものなのでしょうか? 返信の義務はあるのでしょうか?
この記事では、「相続税についてのお尋ね」が届いても慌てないために必要な情報をご紹介します。

相続税についてのお尋ねはいつ来るのか?
「相続税についてのお尋ね」「相続税についてのお知らせ」は、亡くなった人の遺産を相続する相続人に対して送られます。
ご家族が亡くなって相続が発生してから6~8か月が経過した頃に送られてくる場合もあれば、相続が発生してから数年が経過した頃に送られてくる場合もあります。
相続税についてのお尋ねが届くのはなぜ?基準がある?
死亡届を提出すると、市区町村役場は税務署に報告することになっているため、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届く場合があります。しかし、「相続税についてのお尋ね」は、お亡くなりになった方のご遺族、全てに届くわけではありません。
相続税についてのお尋ねは、税務署が「相続税申告の可能性がある」と考えている先に送付されるのです。
税務署は、故人の資産状況を把握できる立場にあるため、資産額の概要を鑑みて、送付先を決定しているようです。とはいっても、この時点では精緻な調査をした上怪しいと判断した先に送付しているというわけではないので、「相続についてのお尋ね」が届いたからといって、特段の心配される必要はありません。
相続税申告の必要がなければ、「相続についてのお尋ね」にその旨の内容を回答し、もし相続税申告の必要があれば、「相続についてのお尋ね」に回答する代わりに、期限内に相続税の申告をしましょう。
相続税についてのお尋ねが届いたらどうすればいい?
相続税についてのお尋ねの封筒の中には「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っていますので、相続税を支払う必要がない方は必要事項を記入して税務署に返送しましょう。
相続税の申告要否検討表の作成を税理士に依頼しなくとも、ご自身で作成することが可能です。相続税の申告要否検討表の記入例については下記をご参照ください。
「記入の仕方がわからない」「相続財産を正確に把握できていない」「相続税の計算のやり方がわからない」といった方は相続に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。
相続税についてのお尋ねが届いてから申告すれば間に合う?
税務署から「お知らせ」などの書類が届いたことで、はじめて相続税がかかるかもしれないと気づく方もいらっしゃいます。しかし、書類が届くのはおおむね相続から半年前後、遅い場合には9カ月もたってから届いたなんて話があるなど比較的ゆっくりです。しかも、これらの書類は、基本的には亡くなった方のご住所に届きますから、書類が来たことに家族は気づかないという可能性もあるのです。
相続税の対象となった場合、申告書は相続開始後 10カ月以内に提出し、相続税は原則現金一括払いです。期限内に申告できない場合は、「無申告加算税」というペナルティが科されます。「無申告加算税」は納付すべき税金の5〜20%。それ以外に「延滞税」という利息のようなものが付きますが、これが年8.9%※(最初の2カ月のみ年2.6%※)と高利貸なみの年率なのです。
※平成30年から令和2年までの期間。利率は期間によって変動します。
>>相続税の申告が遅れた場合のペナルティについて詳しくはこちら
相続税の申告書を作るのはなかなか大変な作業です。
まずは、亡くなった方のすべての財産を確認するところからスタートしますが、一人ひとりの財産をすべて探し出すのは至難の業です。
預金通帳だって複数の銀行で作っていることがありますし、証券会社、保険会社、ゴルフ会員権など、とにかく現金換算できるものは、すべて相続財産です。
最近ではネットバンキングやネット証券なども普及していて、そういうところで口座などを作っていると、家族が探し出せないという可能性もありますし、土地や建物もしっかり調査して相続税の計算のための評価額を決める必要があります。
つまり、税務署からの「お知らせ」などの書類が届いてからでは相続税の申告や納税が間に合わないという方もいるのです。「うちには大した財産がないから多分大丈夫」で済ませずに、本当に相続税がかからないか確認することが大切です。
税務署から届く相続税についてのお尋ねに慌てないための対策とは?
エンディングノートなどを利用して、ご自分の財産リストを把握してみてください。厳密にやろうとすると、面倒くさくなるかもしれませんので、まずはざっくりで結構です。それをもとに、自分に万一があった時に、相続税がかかるのかどうかを確認しましょう。
事前に相続税がかかるとわかれば、節税対策をすることもできますし、納税資金の準備も可能です。また、財産を把握することで、どの財産をだれに残すか、などを考えるきっかけにもなります。是非活用してみてください。
「財産を正確に把握できているか不安…」|相続税に関する無料相談実施中!

ぎふ相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
「相続税がかかるかどうか知りたい」
「相続財産が把握できていない」
「相続税申告が初めてで、何から始めたらいいのかわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に無料相談をご予約ください。
無料相談では、相続の専門家がお客さまのお話をしっかりとお聞ききし、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
当事務所のサポート①簡易相続税シミュレーション
このような方にオススメ
■不動産や預貯金などを、ある程度所有しているが、相続税がかかるかどうかよくわからない
■相続税がかかりそうなので、効果的かつ、正しい相続税の節税対策をしておきたい
■今後、遺言や信託などの生前対策を実施するうえで、将来の争族トラブルが起こらないようにしておきたい
相続税シミュレーションで分かること
■親族関係の調査
相続人となるのは?
法定相続分はどれくらい?
■資産構成の調査
土地、建物の評価額はいくら?
その他資産になるものは?
■相続税の概算と対策の方向性
固定性、流動性資産はいくら?割合は?
納税対策、節税対策として活用できる制度は?
サポート費用
| サービス内容 | サポート費用(税込) |
|---|---|
| ・ご面談・ヒアリング ・必要資料の収集 ・親族関係・資産構成に関する調査の実施 ・相続税試算レポートの作成 ・相続税対策、生前対策のご提案 | 55,000円~ |
| 顧問先様特別価格 | 33,000円~ |
当事務所のサポート②相続税申告
不動産ゼロプラン
プラン料金(税込)165,000円~
相続財産に不動産が無い方におススメしたい相続税申告プランです。
不動産の評価も不要なので、お値打ちな料金でご利用いただけます。
サービス内容
① 相続人の確定
② 財産内容の確認と評価
③ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続税申告書作成・税務署への提出
⑥ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 165,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 220,000円 |
本プランの適用条件
① 不動産件数が0件
②申告期限まで6か月以上
③相続人2名まで(相続人2名の場合は+55,000円)
④遺産分割協議が相続人間で決定済
⑤相続財産の総額が7,000万円未満
⑥被相続人・相続人間の贈与等(預金移動)が無い
⑦銀行・証券口座が3口座以内
⑧証券銘柄多数の場合は別途加算
⑨書面添付制度の利用 +110,000円
>>>相続税申告サポートについて、より詳しく知りたい方はこちら!
スタンダードプラン
プラン料金(税込)275,000円~
サービス内容
① 相続人の調査・確定
② 財産内容の確認と評価
③ 遺産分割協議用の財産目録の作成
④ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
⑤ 二次相続を考慮に入れた節税アドバイス
⑥ 複数の遺産分割協議(案)に応じた相続税額の試算
⑦ 遺産分割協議書の作成
⑧ 相続税申告書の作成・税務署への提出
⑨ 面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 275,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 385,000円 |
| 7,000万円~1億円未満 | 495,000円 |
| 1億円~1.5億円未満 | 660,000円 |
| 1.5億円~2億円未満 | 880,000円 |
| 2億円~2.5億円未満 | 1,100,000円 |
| 2.5億円~3億円未満 | 1,320,000円 |
| 3億円以上 | 別途お見積もり |
相続手続きトータルサポート(相続税申告+手続き)
サービス内容
① 相続人の調査・確定
② 財産内容の確認と評価
③ 遺産分割協議用の財産目録の作成
④ 税務アドバイス(特例適用の可否など)
⑤ 二次相続を考慮に入れた節税アドバイス
⑥ 複数の遺産分割協議(案)に応じた相続税額の試算
⑦ 遺産分割協議書の作成
⑧ 相続税申告書の作成・税務署への提出
⑨ 各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降、1金融機関ごとに3.3万円追加。
⑩面談・電話・メールでの相談、郵送での書類のやり取り
基本料金
| 遺産の総額 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 440,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 605,000円 |
| 7,000万円~1億円未満 | 770,000円 |
| 1億円~1.5億円未満 | 935,000円 |
| 1.5億円~2億円未満 | 1,210,000円 |
| 2億円~2.5億円未満 | 1,430,000円 |
| 2.5億円~3億円未満 | 1,650,000円 |
| 3億円以上 | 別途お見積もり |
加算報酬
加算料金
| 項目 | 加算料金(税込) |
|---|---|
| 相続人加算 | 55,000円(1名追加毎) |
| 土地加算:路線価方式、比準方式 | 33,000円/区画 |
| 土地加算:倍率方式 | 11,000円/区画 |
| 土地加算:特定路線価設定 | 33,000円/1区画 |
| 非上場株式(自社株) | 165,000円/社~ |
| 戸籍他収集 | 3,300円/通 |
| 農地の納税猶予申請手続 | 110,000円/市町村(1名当たり) |
| 農地の相続等の届出書(農業委員会) | 11,000円/市町村 |
| 金融機関の資金移動の調査が著しく複雑かつ煩雑な場合 | 55,000円~ |
オプションプラン
| 項目 | 加算料金(税込) |
|---|---|
| 書面添付制度 | 料金小計×10% (最低料金110,000円) |
| 相続税の延納 | 料金小計×20% |
| 相続税の物納 | 料金小計×30% |
※料金小計=基本料金+加算料金
サポートメニュー
相続手続きに関するご相談をお考えの方へ
相続税申告に関するご相談をお考えの方へ
よくご相談いただくケース
お客様からの声、相談解決実績に関して