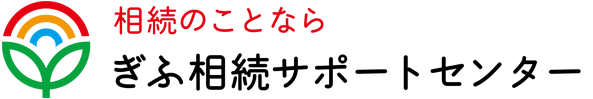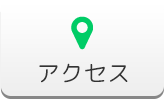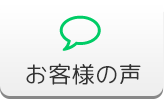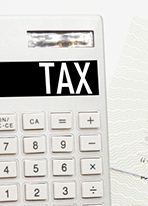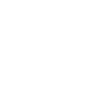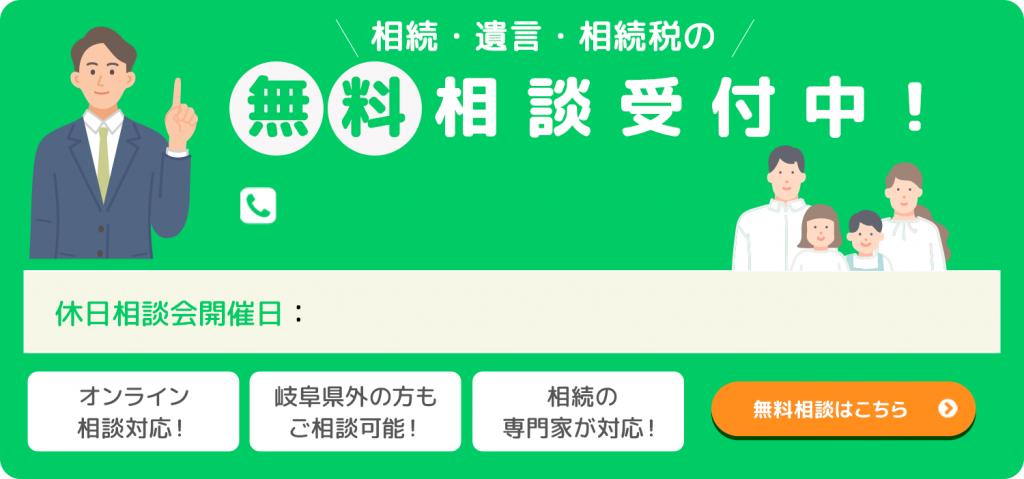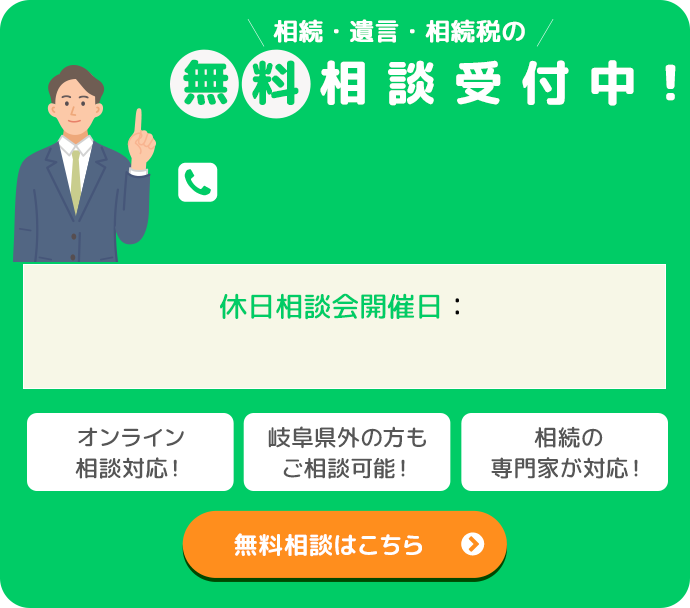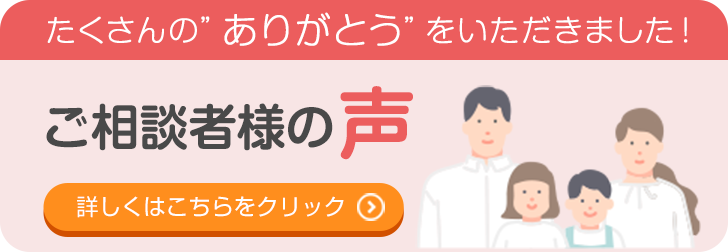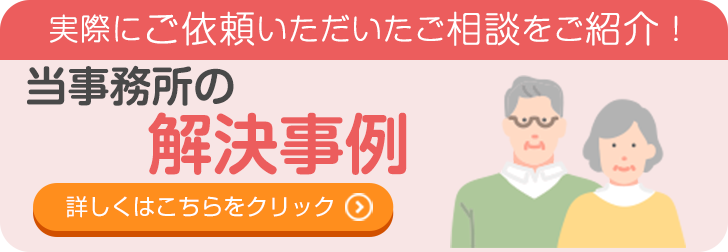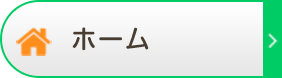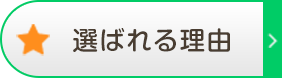未分割でも相続税申告は必要!未分割のデメリットと特例適用の注意点
目次
相続が発生した場合、遺産分割が完了していなくても相続税の申告は必要です。
しかし、未分割の状態で申告を行うことで、特例が適用できなくなったり、余計な税負担が生じたりする可能性があります。本記事では、未分割での相続税申告に伴うデメリットや、特例の適用を受けるための手続きについて詳しく解説します。
未分割の相続税申告でよくあるご相談
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
しかし、期限内に遺産分割協議がまとまらず、相続税申告に間に合わないケースも現実にはあります。このような状況になると、以下のようなご相談がよく寄せられます。
・「遺産分割が終わっていないのに相続税申告は必要?」
・「未分割申告でどのような影響があるの?」
結論から言えば、未分割でも相続税申告は避けられず、期限内に申告をしなければなりません。もし、期限内に申告していない場合、延滞税や無申告加算税が課せられる可能性があるため注意が必要です。
こうした状況下では、未分割申告が有効な選択肢となりますが、少しでも早く遺産分割協議を成立させ、その後の修正申告などを見据えた計画が必要です。
未分割で相続税申告を行う場合のデメリット
未分割のまま相続税を申告する場合、いくつかの特例が適用できないことがあり、相続税の負担が大きくなる可能性があります。以下では、主なデメリットについて解説します。
配偶者の税額軽減が適用できない
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続した財産について、相続税が大幅に軽減される特例です。配偶者の税額軽減を適用できれば、配偶者が実際に取得した財産額が1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額以下のどちらか多い金額までが非課税となり、配偶者が安心して生活を続けるための自宅不動産や資金を確保することができます。
しかし、遺産が未分割の場合、税額軽減の適用ができません。例えば、配偶者が自宅を相続した場合、自宅の評価額が1億6,000万円以下であれば相続税がかからないはずですが、未分割で申告すると税額軽減が適用されないため、相続税が発生してしまうことになります。
小規模宅地等の特例が適用できない
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた宅地や事業用の土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です(適用される面積に上限があります)。例えば、相続した自宅の評価額が1億円で地積が限度面積以内であれば、小規模宅地等の特例を適用すれば評価額が2,000万円に減額、相続税額も大幅に軽減されます。
しかし、未分割のままでは適用できず、宅地にかかる相続税が大幅に増える可能性があります。小規模宅地等の特例が適用されないことで、宅地を相続した相続人が高額な税金を支払うことになり、支払いが難しい場合には、不動産の売却も視野に入れなければなりません。
農地等の納税猶予が適用できない
農地を相続する場合、一定の条件を満たせば相続税の納税が猶予される特例があります。納税猶予を適用することで、農業を継続する限り、相続税の納付が先送りされ、場合によっては納税が免除されることもあります。
しかし、農地等の納税猶予は、遺産分割が完了していることが条件となっているため、未分割の場合には適用されません。農業を続けたい相続人にとって、納税猶予を受けられない事態は避けたいものです。農地を手放さないためにも、できるだけ早く遺産分割を完了させ、適切な手続きを行う必要があります。
非上場株式等の納税猶予・免除ができない
中小企業の非上場株式を相続する場合、事業を継続する条件で納税猶予や免除が適用されます。
しかし、遺産が未分割のままだと、納税猶予・免除が適用されないため、相続税の負担が大きくなる可能性があります。事業承継において、株式の相続税が高額になると、事業継続が難しくなる場合があります。未分割で納税猶予が適用されないと、事業資金に充てるはずの資産が税金に消えてしまうため、早急に分割協議をまとめることが求められます。
物納の利用ができない
物納とは、相続税を金銭ではなく、不動産などの財産で納める制度です。
しかし、未分割の財産は相続人全員の共有財産とみなされ、物納が認められないため、金銭での納付が求められることになります。特に、不動産が大部分を占める相続では、物納の利用が難しくなることが大きな問題となります。
預貯金や現金がほとんど相続財産に含まれない場合、不動産の売却によって納税資金を用意しなければならないケースも多くなっています。また、不動産は現金と比較すると分割が難しいため、遺産分割を巡るトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。
遺産の大部分が不動産という方は、遺産分割協議が長引くことを想定し、早めに話し合いを進めることをおすすめします。場合によっては、専門家の介入も視野に入れましょう。
申告期限後3年以内の分割見込書を提出する際のポイント
未分割で相続税を申告する場合、特例の適用を後で受けるためには、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが必要です。
分割見込書を提出しておけば、3年以内に遺産分割が完了した場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用させることができます。
また、分割見込書を提出する際には、以下のポイントに注意しましょう。
・分割が遅れている正当な理由を記載する
・分割の見通しや進行状況を明確に説明する
・適用を希望する特例についても明記する
なお、やむを得ない事情がある場合に限り、申告期限から3年経過してしまっても、特例の適用をさらに延長させることは可能です。ここでいうやむを得ない事情とは、遺産分割が裁判にまで発展している場合や遺言で一定期間遺産分割が禁じられている場合などです。
更生の請求を行う場合の注意点
遺産分割が成立した後、未分割申告で申告した相続税の還付を受けるためには、更生の請求を行う必要があります。
更生の請求
更生の請求とは、納めすぎた相続税を取り戻すための手続きです。
遺産分割協議が成立し、各相続人の取得する財産が確定すれば、納めるべき税額についても確定することになります。あらかじめ分割見込書を提出していて、後から特例を適用させることができれば、未分割の状態で納税していた税額を取り戻すことができます。相続税額が大幅に変わることもあるため、必ず更生の請求を行いましょう。
未分割の場合でも申告は必須!専門家に相談を!

未分割の状態であっても、相続税の申告は期限内に行う必要があります。
未分割で申告を行うと、特例が適用できず、相続税が増えてしまうため、可能であれば申告期限内に遺産分割協議を成立させることが重要です。もし、成立が難しい場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、後から更生の請求や修正申告を行うことで、特例を適用させることが可能ですが、分割されていない理由、やむを得ない事情の説明など、未分割での申告には複雑な手続きが伴うため、税理士に相談することをお勧めします。
未分割の相続トラブルにお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
- 相続税の路線価と評価方法を解説!計算方法や補正のポイント
- 相続した不動産の相続税評価額について解説!
- 未分割でも相続税申告は必要!未分割のデメリットと特例適用の注意点
- マンションの相続税について
- 相続税申告が不要か判断する場合の注意点
- 小規模宅地等の特例の「同居」とは?様々なパターンを徹底解説!
- 土地を相続したら小規模宅地の特例を使いましょう!
- 小規模宅地等の特例で大幅節税へ!要件や事例をわかりやすく解説!
- 相続税の申告を税理士に依頼した方が良い理由
- 家なき子特例とは?適用条件や必要書類についてわかりやすく解説!
- 相続税は土地評価額を下げて大幅節税!対象になる土地20選
- 申告期限が近付いているという方へ
- 相続手続きトータルサポート(相続手続き+相続税申告)
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 税金の各種控除について
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 【税理士が解説】相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 【税理士が解説】相続税の申告を税理士に依頼する理由とは?5つのメリットを紹介
- 【税理士が解説】相続財産別の相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
サポートメニュー
相続手続きに関するご相談をお考えの方へ
相続税申告に関するご相談をお考えの方へ
よくご相談いただくケース
お客様からの声、相談解決実績に関して