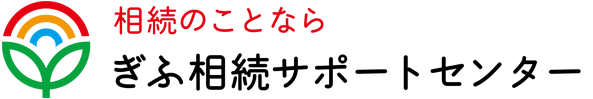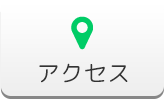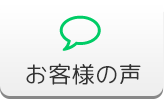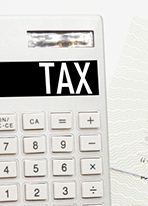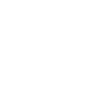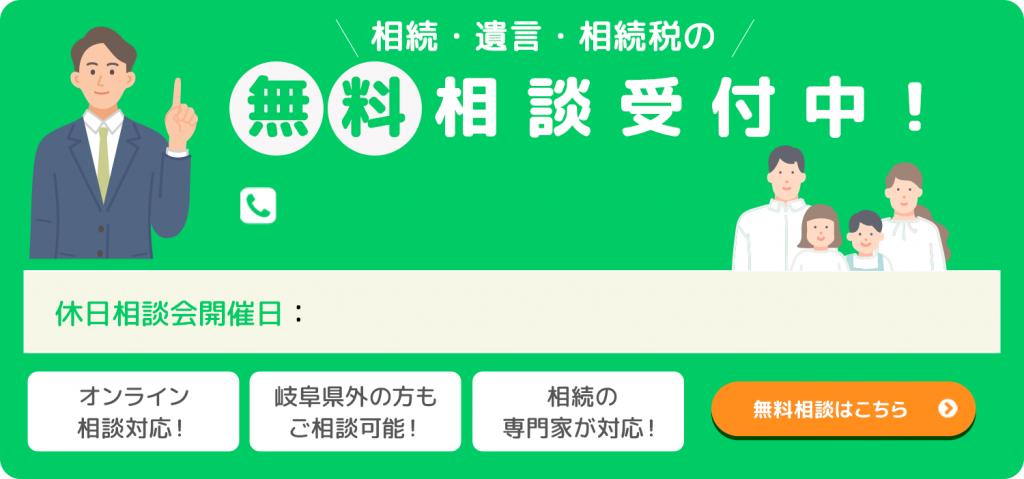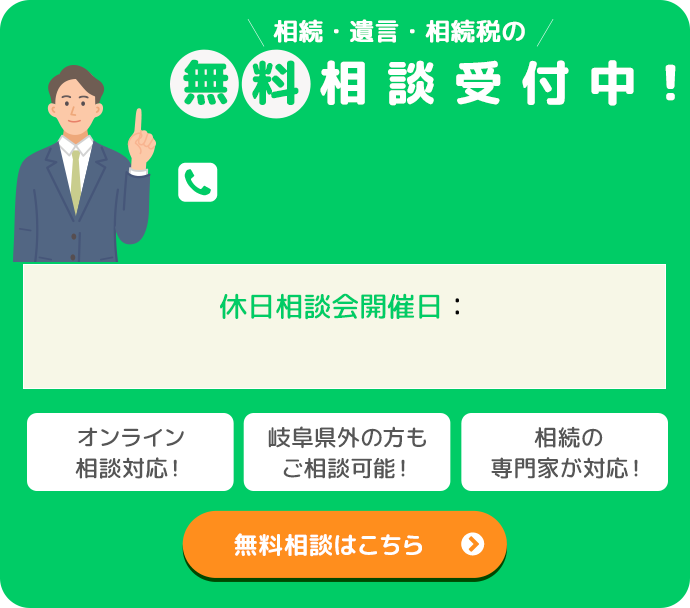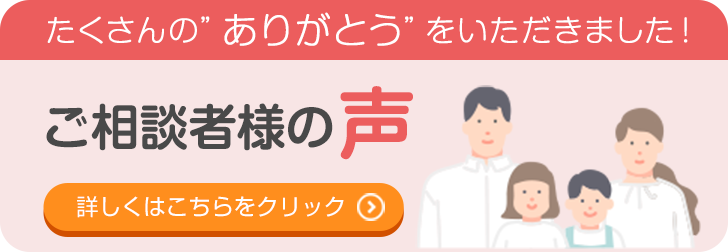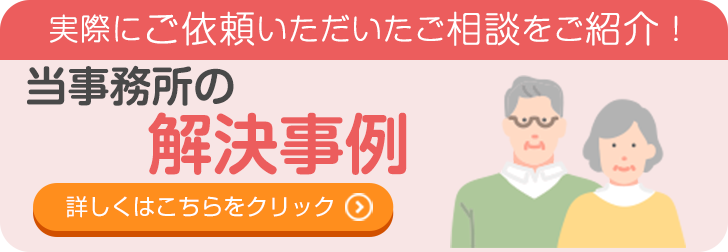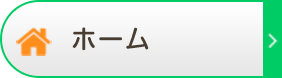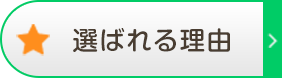小規模宅地等の特例の「同居」とは?様々なパターンを徹底解説!
目次
小規模宅地等の特例は最大で80%も宅地の評価額を下げることができるため、適用できるなら活用したい制度です。
小規模宅地等の特例の条件に「同居」と記されていますが、どのようなパターンが同居になるのでしょうか?
この記事では、この「同居」とは具体的にどんなケースが当てはまるのかを解説していきます。
目次
1.小規模宅地等の特例で「同居」はなぜ重要?
被相続人が住んでいた宅地を相続する場合に、「特定居住用宅地」として小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのは、次に該当する人です。
1.被相続人の配偶者
2.被相続人と同居していた親族で、相続開始時から相続税申告期限まで継続してその自宅に住み続け、かつ、その宅地等を所有している人
3.被相続人と別居していた親族で、家なき子特例(※)の要件に該当する人
被相続人と同居していた親族が宅地を相続する場合に、特定居住用宅地等に該当するかどうかは「同居」が鍵となります。
2.小規模宅地等の特例の同居の要件
同居親族とは、被相続人が亡くなる直前に、同じ家で一緒に日常生活を送っていた親族のことをいいい、 これを法律上「共に居起していた」といいます。
(1)実務上の4要件
・日常生活の状況
・家へ入居した目的
・家の構造及び設備
・その親族の生活拠点となる他の家の保有状況
同居の定義は、以上の4つの観点から判断されます。
(2)同居期間についての要件はない
小規模宅地等の特例の居住用宅地等では、宅地を相続する親族が相続開始の時点から相続税申告まで継続して被相続人の自宅に居住する必要がありますが、被相続人と同居認められるために必要な年数・期間についての要件はありません。
ただし、次項からご説明するように、あくまで実態で判断されるので、外見上似たようなケースであっても、「同居」となるケース、ならないケースがあります。
3.小規模宅地等の特例で「同居」になる事例
(1)完全分離型の二世帯住宅
同じ建物の中で親と子供世帯が暮らす二世帯住宅は以下の3種類の形があります。
1.完全同居型
2.部分共有型
3.完全分離型
3の完全分離型はマンションの隣同士で生活するようなイメージで、全く別の世帯として暮らす構造になっており、同居ではないだろうと考えてしまいますが、同居として認められます。
以前は、二世帯住宅であっても完全分離型の場合には同居とは認められませんでしたが、税制改正により2014年から二世帯住宅の構造は問われなくなりました。
(2)相続人が単身赴任で別居中
被相続人と相続人一家は同居しており、相続人だけ単身赴任で別居していた場合でも、被相続人と相続人は同居として認められます。
その理由は、相続人は家族を残して単身赴任していることから、単身赴任が終わればまた相続人も被相続人と同居することが明らかであり、現状は別居であっても、生活の基盤は被相続人と家族が生活している家にあるとされます。
(3)被相続人の死亡後に相続人が単身転勤
被相続人の死亡後、相続税の申告期限前に相続人が転勤で単身赴任先へ引っ越すことになったケースでは、被相続人の死亡時点では同居をしていますが、申告期限までその家に住んではいません。
この場合には、前項と同様に、家族を残して単身赴任しているため、生活の基盤は被相続人と家族が同居していた家にあると考えられ、申告期限まで引き続き住んでいると認められます。
ただし、家族ごと引っ越してしまった場合には、申告期限まで住んでいないうえに生活基盤も移してしまったと考えられ、小規模宅地等の特例は適用できません。
(4)被相続人が老人ホーム入居中に死亡
被相続人が老人ホームに入居し、そのまま退所することなく死亡した場合でも、同居していた相続人がそのままその家に住み続ける場合には、同居として認められます。以前は認められなかったものが、2014年度税制改正により認められるようになりました。
しかし、「被相続人が老人ホームに入居した家を賃貸した」「被相続人が老人ホームに入居した後に経済的に独立した親族がその家に住み始めた」などの場合は、同居として認められません。
4.小規模宅地等で「同居」にならないケース
(1)区分登記している二世帯住宅
二世帯住宅について、構造は問われないと解説しましたが、どのように登記されているかは小規模宅地等の特例の適用を受けるために重要となります。
二世帯住宅を親子で区分所有登記している場合には、同居として認められません。
例えば、二世帯住宅で1階と2階を分けて親子で同居している場合、建物をすべて同じ名義で登記せずに、別々に登記しているケースです。建物すべてを親子で半分ずつ共有で所有する共有登記は同居の扱いになります。
(2)住民票は同じだが、実際は別居しているケース
被相続人と同居していたかどうかはあくまで実態ベースでの判断となります。
住民票が同じであっても、日常生活を共にしていばい場合は同居と認められません。逆に、実態は同居していたが、住民票が別の場合は同居として認められます。
税務署は、郵便物の送付先、水道光熱費、近所への聞き込み、勤務先への通勤状況などから実態を把握することができます。
(3)介護するための同居
被相続人と別居している親族が、被相続人の介護のためにその家に泊まって生活していた期間中に被相続人が死亡した場合は、同居と認められません。被相続人死亡後も遺品整理などのために、申告期限まで住み続けたといったケースも認められません。
(4)週末だけ同居
平日は相続人家族で日常生活を送り、週末だけ被相続人のもとで生活している場合は、生活基盤は相続人の家だと判断されるため、同居として認められません。
5.まとめ
この記事では「同居」と考えられる様々なケースについて説明してきました。
「同居」という定義は、税法上は明確な定義がありません。上記で説明した通り、実態を実務上の4要件をもとに総合的に判断されます。
税務調査が入った場合は、水道光熱費や郵便物の送付先など細かいところまで調べられるので、同居の判断をする場合は、専門家に相談しましょう。
小規模宅地等の特例をお考えの方向の無料相談実施中!

相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-380になります。
お気軽にご相談ください。
- 相続税の路線価と評価方法を解説!計算方法や補正のポイント
- 相続した不動産の相続税評価額について解説!
- 未分割でも相続税申告は必要!未分割のデメリットと特例適用の注意点
- マンションの相続税について
- 相続税申告が不要か判断する場合の注意点
- 小規模宅地等の特例の「同居」とは?様々なパターンを徹底解説!
- 土地を相続したら小規模宅地の特例を使いましょう!
- 小規模宅地等の特例で大幅節税へ!要件や事例をわかりやすく解説!
- 相続税の申告を税理士に依頼した方が良い理由
- 家なき子特例とは?適用条件や必要書類についてわかりやすく解説!
- 相続税は土地評価額を下げて大幅節税!対象になる土地20選
- 申告期限が近付いているという方へ
- 相続手続きトータルサポート(相続手続き+相続税申告)
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 税金の各種控除について
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 【税理士が解説】相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 【税理士が解説】相続税の申告を税理士に依頼する理由とは?5つのメリットを紹介
- 【税理士が解説】相続財産別の相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
サポートメニュー
相続手続きに関するご相談をお考えの方へ
相続税申告に関するご相談をお考えの方へ
よくご相談いただくケース
お客様からの声、相談解決実績に関して